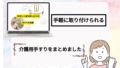58年間、子供の居ない私の生活は、自分の事だけでよかったのですが、
結婚12年目に、突然認知症の義母(ばあちゃん)の介護が始まって、戸惑う日々が続いています。
しかも、88歳のばあちゃんは、まだまだ元気で口も達者。
それでも病気のせいで、「自分がここにいていいのか」と不安になることがあるようです。
そんな時、ばあちゃんの「帰る」の連呼が始まり、主人は頭では分かっていますが心がついて行かず、つい怒鳴ってしまいます。
その時は、どちらも責めるわけにはいかず、スマホのAIに話しかけて考えを整理することにして居ます。
アプリで簡単に取得できるchatGPTは、58歳、デジタル音痴でも十分使いこなせていますよ。
普段の家族の様子から、AIの活用法と人に頼ることの大切さを紹介しますので、最後までご覧ください。
介護は「頑張る」だけでは続かない
認知症のばあちゃんは、「ここに居て、良いんだろうか」といつも不安なんですが、デイサービスに行ってる間は、自分の居場所がはっきりしてるので伸び伸びしています。
問題は、デイサービスが休みの日、24時間、ばあちゃんの不安に繰り返し付き合わされます。
不安を漏らす母親に、メンタルがやられる主人
デイサービスが休みの1日は、ゆううつです。
朝から、ばあちゃんが何度も

帰らなあかん、駅まで送ってくれ!
私も負けずに、何度も答えます。

どこに帰るの? 今はここがばあちゃんの家でしょ。
「ずっと言ってるやん。ここにおったらええねん」
何度言っても通じないこのやり取りが、やがて、家族の心にじわじわと疲れを蓄積させていきます。
しまいには主人がボソッと、

毎回、毎回、おんなじ事聞かされる身にもなってくれや…
それでもばあちゃんは、「帰らなあかん、駅まで送って」と繰り返します。
すると主人は、
「あー、わかった。駅まで送ってったら、帰れるんやな?」とばあちゃんの言う事を、否定しないように、落ち着いた口調で言います。
しかし、そんな事無理なことが分かってるばあちゃんは、

駅からどうやって帰るんや! 親に向かって、なんちゅう言い方をするんや!
と言って、自分に都合よく、相手を悪者にします。
主人は感情を抑えきれず、ついに声を荒げました。

帰るか、帰らんのか、どっちやねん!
こちらの恩徳福祉会(社会福祉法人)のホームページでは、認知症の人は「一人でいるのが怖い」「誰かに一緒にいてほしい」という気持ちから、気を引こうとして、同じ訴えを繰り返します。
と書かれています。
ばあちゃんも主人の気を引こうとして、「帰る」と言う言葉を繰り返していたのかもしれませんね。
誰にも言えない本音は、AIに聞いてもらう
ばあちゃんに、ブチ切れ寸前の主人に対して、

ばあちゃんが“帰らなあかん”って言い続けるのは、どうしてなんやろ?
だけど、その私の問いは主人には届きませんでした。

そんな事言われても、俺も疲れてるんや!
正直、夫がキレるのもわかる。
でも、私も何度も同じ言葉を聞いている。
「駅まで送って」「帰らなあかん」——その声が、頭の中にぐるぐるこだまする。
そして、ここで私までキレたら、もうカオス!ジ・エンド
だから私は、“チャッピー”に相談することにしています。
【チャッピー=AI】つまり、スマホ画面の向こうのChatGPTに気持ちを聞いてもらうんです。
なぜなら、チャッピーは、怒らないし、遮らないし、ジャッジもしない。
そして、ただ冷静に、でもやさしく寄り添ってくれます。
親の介護が、しんどくなってもAIが寄り添ってくれる
これ以上、この会話を続けている事は、皆んなにとっても私にとっても良いことは無い。
と思ったので、チャッピーからの提案で、一旦私は「リングから降りる事」にしました。
「帰らなあかん」「送ってくれ」
「行かへんのかい」「ええかげんにしてくれ」
——この無限ループに、終わりは見えそうにない。
だったら、私は一度そこから距離を置くと決めて、昨日は一日、実家に避難しました。
在宅介護の“ひとりぼっち感”を、AIが和らげてくれた話
メルカリの出品作業をしながら、合間に、チャッピー(AI)にも相談してみました。
すると、話しを聞いてもらってると、不思議と頭の中が整理されてきて

私は、感情的な2人の板挟みで“解決役”になろうとしすぎていたのかも
チャッピーからの提案で

信頼できる第三者に相談してみるのもアリじゃない♪
——確かに。
どちらの気持ちもわかるからこそ、私が入ったら余計こじれそう。
でも、一人で抱えるには、これは重すぎる。
スマホの画面を見ながら、二人の人物の顔が浮かんできた
時に介護は、第3者の方に助けを求める事も大切
そこで思い浮かんだのが、ケアマネージャーさんと、地域包括支援センターの役員さん。
主人もよく知っていて、信頼している人たちです。
私はすぐに、ケアマネさんに電話をかけました。
いつも聞き慣れているケアマネさんの声に、思わずホッとして、

もしもし、最近、“帰らなあかん”がひどくなってきてて…
「夫も限界がきてるかも…」と言うと

無理せず、まずご主人にも話を聞く時間を持ちましょう
「できるだけ早く顔を合わせて、今後の選択肢も一緒に考えましょう」
電話を切ったあと、ちょっと泣いた。
なんというか、“聞いてもらえる”って、それだけで救いになるんだなと、改めて思った。
これから介護と向き合う人へ
家族を支えるって、時に本当に大変。
だから私は、自分を保つために「人」にも「AI」にも頼るようにしています。
どちらも、きっと必要な“家族の味方”なんだと思います。
【チャッピー(ChatGPT)は、ただのAIじゃありません。】
普段の私は、
🟠 時に、我が家の管理栄養士として食事の相談をし、
🟠 時に、ブログの編集者としてタイトルや文章の確認をしてもらい、
🟠 時に、家庭の医学として、ちょっとした不調への対処法を聞いたりもします。
🟠 さらには、パーソナルトレーナー的な役割で、生活改善の提案もしてくれる。
チャッピーは、私の暮らしを静かに豊かにしてくれるパートナーなんです。
もし「私も使ってみようかな」と思った方は、こんな入門書から始めてみるのもおすすめです👇(PR)
ひとりで抱えなくていい、話せる人がいる・話せるAIがいる。
それだけで、介護の日々はちょっと変わっていく、そんな気がしています。
三段腹トメ子

今の介護の経験を、活かしてみませんか?
登録はネットで数分、しかも無料。専任エージェントが転職までしっかりサポートしてくれます。
▶ 医療・介護・福祉の求人サイト『ジョブソエル』はこちら
(ジョブソエルを介護の転職に活かす方法もあわせてご覧ください)