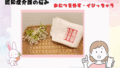今年、母は83歳になります。
私の勧めで、長年使っていたガラケーからスマホに替え、今では毎日、パズル系のゲームに夢中です。
でも、LINEで文字を打ったり、設定をいじったりするのは、やっぱり苦手みたい。
そんな母ですが、持病の管理のため、日課のように病院に通っています。
高血圧、目薬、三叉神経痛の薬、そして脳腫瘍の経過観察……。
通院の理由は、年を重ねるごとに増えていきます。
もちろん、いつも私が付き添って、受付も一緒に済ませています。
マイナンバーカードを保険証として使うようになってからは、病院のあの“ピッとする機械”も、私がそばで「ここを押して、次はこれ」とガイドするのが定番でした。
でもある日、私がどうしても外せない用事で出られず、代わりに主人にお願いすることに。
問題は……うちの主人も、母に負けず劣らずのデジタル音痴。

さて、マイナカードでの受付はうまくいったのでしょうか?
🏥 マイナンバー保険証の使い方(病院受付での基本的な流れ)
| 手順 | 操作内容 | 声かけの例(トメ子さん用) | 補足ポイント |
|---|---|---|---|
| ① | カードを機械に置く | 「ここにカード置いてね」 | 裏表・向きがあるので注意 |
| ② | 顔認証 or 暗証番号を選ぶ | 「顔を選んでみて」 (暗証番号も選べるよ) | 暗証番号がわからない場合は顔認証が安心 |
| ③ | カメラに顔を向ける | 「ゆっくり顔を近づけて」 | 帽子・マスクは外した方が反応しやすい |
| ④ | 利用目的の同意を求められる | 「“同意する”を押していって」 | 「すべて同意」ボタンが出ることもある |
| ⑤ | 完了の画面が出たら終了 | 「終わったよ、おつかれさま!」 | 受付に行くか、番号札が出てくる |
「82歳の母ができた!」という小さな成功体験
マイナンバー保険証の本格運用は2021年10月20日から始まりました。
今は2025年6月なので3年とちょっと経ちました。
「え、そんなに」
私もびっくりです。
慣れないマイナンバー保険証、娘がいれば大丈夫

母にとっては「娘がいれば大丈夫」──そんな安心感があるようです。
実際、通院のたびに私はこう声をかけています。
「ここにカード置いて」
「次は、顔認証を選んで」
(※暗証番号入力でもできるけど、母はいつも“顔”を選びます)
「で、全部“同意する”を押して…はい、完了!」
母は何度も「難しいなあ」と言いながらも、私の声かけに合わせてボタンを押すのがルーティン。
一人では不安でも、隣にいる“この子”が一緒なら、デジタルも怖くない──
そんな顔をしているのが、ちょっと嬉しい。
「今日は一人でやれたでー」嬉しそうな母の顔
マイナンバー保険証の運用が始まってから、自分でも使ってきました。
母とは、何度も一緒に病院へ行き、何度も機械の使い方を練習してきました。
最初は毎回つまづいていた操作も、今ではほとんど声かけだけでスムーズにこなせるように。
「ここに置いて」「顔認証を選んで」「全部、同意する」
そんな流れを繰り返すうちに、母の中に“やり方の型”ができていたのかもしれません。
だから今回、デジタル音痴の主人と二人でちょっと不安はあったけれど、

まあ、大丈夫やろう
そして、帰宅した母は
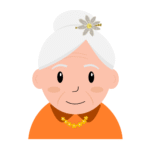
今日は、一人で出来たよ!
うちの母は、ここまで来るのに何度も練習して、そばに誰かがいたからこそ乗り越えられた。
でも、他の高齢者やデジタルが苦手な人にとっては――
こんな“ちょっとした操作”でも、大きな壁に感じている人がたくさんいるんじゃないかと。
デジタルに苦手意識があるのは、高齢者だけじゃない
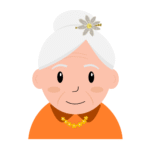
「今日は一人でやれたでー!」
そう言って、嬉しそうに帰ってきた母の顔を見て、私も「ホッ」とひと安心。
でも同時に、ふと思ったんです。
うちの母は、何度も練習してやっとここまで来た。
じゃあ、他の高齢者や、デジタルに苦手意識がある人にとっては――
病院の受付機ひとつ取っても、ちょっとした操作がハードルになっているんじゃないかと。
たしかに、今はなんでも便利な世の中。
マイナンバー保険証も、慣れればスムーズだし、受付の混雑も減って合理的です。
けれど、「便利さ」と「安心感」は、必ずしもセットじゃないのかもしれません。
実は、うちの義息子も、いまだにマイナンバーカードを作っていません。
理由は「めんどくさいから」。
高齢者と違って、スマホも使えるし、仕事もしてる世代です。

これから、どんどん制度も暮らしも便利になっていくよー。
82歳の母や、68歳の主人は、まだ「誰かがやってくれる」って立場でいられる。
でも、私は今年58歳。
同年代の友人たちと話してても思うんです。

私らって、“めんどくさい”で止まってる場合ちゃうよね
これから先、介護保険も、医療費も、年金も、自分が“使う側”になる制度がどんどん増えてくる。
その時に、「制度がどう動いてるのか」
「何を準備しておくとラクになるのか」
それを“知ってるかどうか”で、老後の安心感がまったく違う気がするんです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
三段腹トメ子