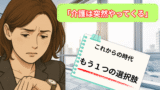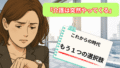イチロウの介護保険外サービスを本当に知ってもらいたいのは、今、このブログを読んでいる“あなた”です。
前回【もうムリ!そんな時『イチロウの介護』がお手伝い】では、「こんな時にどう使えるのか?」を、私自身の体験を交えて紹介しました。
さらに、『全国ビジネスケアラー会議 仕事と介護、両立のヒントがここに。』(株式会社チェンジウェーブグループが主催)の記事を読んで、改めて気づいたんです。
今の介護にはカバーしきれない部分が多いことに。
そして、その忙しいビジネスケアラーが抱える問題こそ、イチロウなら解決の糸口になるのでは?と希望を持てました。
今回は、想定できる場面を例にしながら、介護の不安をどう解消できるのかをご紹介します。

この記事が「仕事と介護の両立」のヒントになります。
ぜひ最後までご覧ください。
『介護と仕事』の両立を叶える介護の形とは
『ビジネスケアラー』という言葉、知っていますか。
これは、働きながら親や家族の介護をしている人のこと。
実は、日本では約300万人以上がこの立場にあると言われています。
現代が抱える問題(ビジネスケアラー)
例えば…..
Aさんは都内に住む40代の独身男性。
仕事は忙しく、プロジェクトの締め切りや部下の育成に追われる毎日。
平日は、夜遅くまでオフィスにいるのが当たり前の生活をしています。
ある日、妹から一本の電話がありました。

「お兄ちゃん、お母さんの様子がおかしいの」
「さっきお母さんから電話があって、“お父さんが朝から帰ってこないの”って…」
妹は同じ千葉県内に住んでいますが、すでに結婚していて3人の子どもを育てています。
小学校から中学校まで子どもの行事も多く、家事や育児に加えて週4日のパート勤務もして日々、時間に追われた生活をしています。

実は、父は3年前にすでに他界しています
一瞬、背筋が凍る感覚にーー
これが、まさに今増えている“ビジネスケアラー”の問題です。
私がビジネスケアラーに対する問題点を挙げるなら
認知症による介護は、思った以上に家族に負担がかかります。
特に初期の段階では気づかれにくく、介護保険に繋がる前に病状が進んでしまうこともあります。
以前書いた【明石市民が「オレンジサポータ」を受ける意義は】の記事では、「認知症を知ることが、未来の自分を守る」と紹介しました。
ここでは、ビジネスケアラーが直面しやすい問題点を5つにまとめます。
- 時間が圧倒的に足りない
仕事と介護を両立しようとすると、一日24時間ではとても足りません。 - 職場に理解してもらえるか分からない
介護で休むことを言いにくく、隠して働き続けてしまう。 - 情報不足で迷子になる
介護保険の制度は分かりにくく、どこに相談すればいいのか、。 - 精神的な負担が大きい
親の変化に直面するショックや罪悪感がのしかかる。 - 経済的な不安
サービス費や交通費がかさみ、将来の収入への不安も強い。
イチロウがくれる“もう一つの選択肢
「親が認知症かも」
「これから介護が始まるのかも」

そう感じたとき、まだ介護保険に繋がっていないこの時期が、実は一番しんどいんです。
何をどうすればいいのか分からない。
病院?役所?会社?どこから動けばいいのか見えない。
そんな不安に押しつぶされそうになるのは、誰にでも起こり得ることです。
だから、介護経験のある私からのアドバイス。
焦らないことです。
イチロウの選択は、公的支援をベースに考えて
介護が始まるかもしれないと感じたとき、まず押さえておきたいのは 公的な支援をベースにすること です。
介護保険や地域包括支援センターは、「制度が複雑で分かりにくい」と思われがちですが、最初の相談先として必ず役に立ちます。
頼れるところを知ろう
大切なのは、次の3つのステップ。
地域包括支援センターに連絡する
まずは、地域包括センターに相談して。「最近、母の様子が少し変で心配です」と伝えるだけで大丈夫。
地域包括支援センターは、高齢者や家族の相談窓口として全国に設置されています。
認知症の不安や介護保険の申請手続きなど、最初の一歩をサポートしてくれる場所です。
👉 詳しくは、厚生労働省の公式ページも参考にしてみてください。
職場に正直に伝える準備をする
いざという時、都合がつけられる様に仕事場には状況を上司や同僚に早めに共有しておく事は大切です。
隠してしまうと、突然休まざるを得なくなった時、職場に迷惑をかけてしまうこともあります。

理解を得るためには、まず自分から、小さく打ち明けておくことがポイントです
家族だけで抱え込まない
「全部を家族でやろう」と思わないことが大切です。
親の介護は、突然始まることが多いもの。
何もかも初めてのことばかりで、不安に思うことも少なくありません。

だからこそ、
地域の民生委員やボランティアの人、何でも頼って良いんです。
そして、その一つの選択肢として『イチロウ』のような介護保険外サービスがあります。
自由度の高いオーダーメイド型のサポートで、「保険だけではカバーできない部分」を埋めてくれます。
詳しくはこちらの記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
初め”イチロウ”を利用するタイミング
親の様子に「あれ?」と違和感を覚えて、地域包括センターに連絡しても、すぐに支援につながるとは限りません。
たとえば、Aさんのように都内で仕事をしていて、お母さんは千葉で一人暮らし。
すぐに駆けつけられない、妹にも負担をかけられない。

そんな時に頼りになるのが「イチロウ」です
自由度の高い介護保険外サービスなので、実費にはなりますが、その分、必要なサポートをしっかりお願いできます。
\まずはお気軽にご相談ください/
子世代が知っておきたい|介護のポイント
介護認定が降りて、介護保険が使えるようになっても、介護度によって、受けられるサービスの範囲が決まっています。
例えば、

要介護2の義母は、
費用の安い特別養護老人ホームへの申し込む事はできません
そこで改めて認定審査を受け、要介護3と判定されて、ようやく特別養護老人ホームへの申し込みが可能になったのです。
このように介護度によって利用できるサービスには制限があり、「必要なのにすぐには使えない」というケースも出てきます。
そのような場合、自由度の高い『介護保険外サービス』を利用する方法です。
さらに、身近で役立つ「介護グッズ」を取り入れるのも大きな助けになります。
イチロウ以外に、知っておきたい介護用グッズ
人気の見守りカメラ
「離れた部屋でも親の様子を見たい」「夜間の変化を知りたい」「不安な時に声かけで安心させたい」。
このような介護における見守りのニーズに、「パナソニック ベビーモニター KX-HC705-W」は安心感と手軽さを追求した、最適な一台としてお応えします
iimono117 介護用 手すり
工事不要で設置できる“置くだけタイプ”の手すりです。
トイレや立ち座りが不安な場面で役立ちます。壁や床に穴を開けずに使える手軽さが魅力です。
先に紹介したグッズ以外にも、Tシャツにバーコード(QRコード)を貼り付けて徘徊に備えるのも一つの方法です。
実は、私も義母のためにこの方法を試しました。
「カニくん|Tシャツプリント」に依頼して、QRコード入りのオリジナルTシャツを作ってもらったんです。
いざという時、周りの方がスマホでQRコードを読み取れば、すぐに連絡先が分かる仕組み。
着るだけで“もしも”に備えられる安心感があるので、介護保険サービスや介護グッズと併せて検討する価値があると思いました。
40歳から遠距離介護する男性に学ぶ
2012年から親の介護を続けている、くどひろさんの介護が始まったのは、彼が40歳の時でした。
彼のブログ『40歳からの遠距離介護』には、数々の介護の工夫や実践が記されています。
その中の1つが、『「要介護認定」を受ける時の3つのコツ』
親御さんが正しく判定してもらうためには、普段の様子をきちんと記録しておくことが大事だと書かれています。
要介護認定あるある
認知症の方の場合、調査員が訪問したときに限って“いつも以上に頑張ってしまう”。
その結果、実際の生活状況よりも軽く見られてしまい、思ったような介護認定が降りない…(汗)というケースは少なくありません。
イチロウを活用するなら
例えば「見守りサービス」をイチロウにお願いしたとき、こんな活用法もあります。
一緒に買い物に行った際の様子を、さりげなくチェックしてもらう
- 同じものばかりを買っていないか
- お財布から自分で支払いができているか
こうした普段の様子を第三者が記録しておくことで、要介護認定の審査がスムーズになることもあるんです。
このブログには、くどひろさんの積み重ねられた リアルな工夫と知恵 が詰まっています。
自分を犠牲にしない介護を
介護は、親や家族を支えるために全力を尽くしたくなるものです。
でも、自分を犠牲にしてしまうと、結局は誰も幸せになれません。
無理をせず、地域包括センターや介護保険、そして「イチロウ」のような介護保険外サービスや介護グッズを上手に組み合わせること。
頼れるものは頼っていいし、周囲に助けを求めることは決して“甘え”ではありません。
介護を続けるために一番大切なのは、あなた自身の生活と心の余裕を守ることです。
その余裕があってこそ、親にも優しく寄り添えます。
介護は突然やってくる。
公的支援+イチロウ+工夫で“自分も大切にできる介護”は可能です。