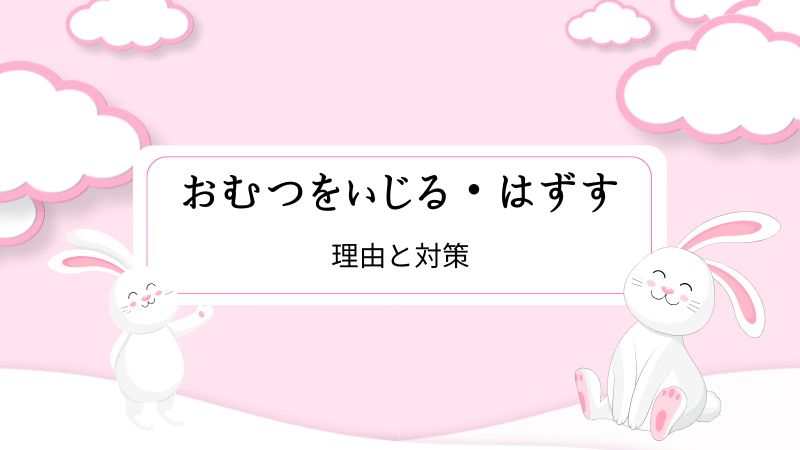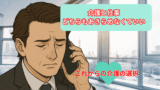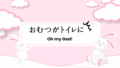以前、トメ子さんに、お義母様の介護エピソードを伺いました。
そのお話は【認知症の親が「おむつは必要ない!」と拒否、介護者にできること】の記事で紹介しました。
今回は、その中で触れきれなかった『認知症のおむつ外し』について。
トメ子さんが子どもの頃に見た『母と祖母の介護』から、今の時代に続く『おむつ外し対策』までをまとめました。
気軽に読める内容です。
最後まで読んでもらえれば、将来の介護にきっと役立ちます。
※介護保険ではカバーできない「通院付き添い」や「夜間見守り」などに対応する民間サービスを紹介しています。
認知症介護の経験は、母から娘へ
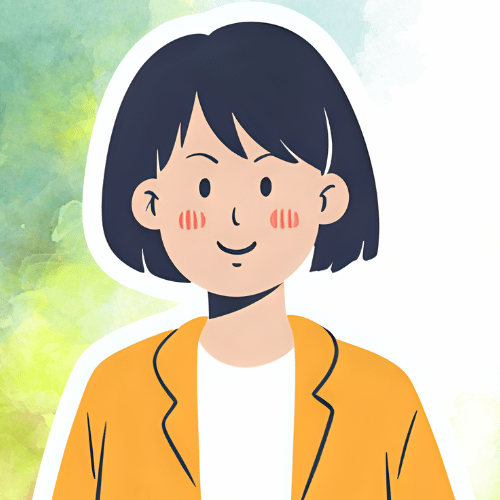
お義母様の介護、お疲れ様でした。今回は、どのようなお話ですか?

今回のテーマ『おむつ外し』は、実は私自身の子供の頃からつながっている話なんです。
そう言って、トメ子さんは、昭和の家の台所や、午後の光が差し込む畳の部屋を思い出すように、ゆっくりと話し始めました。
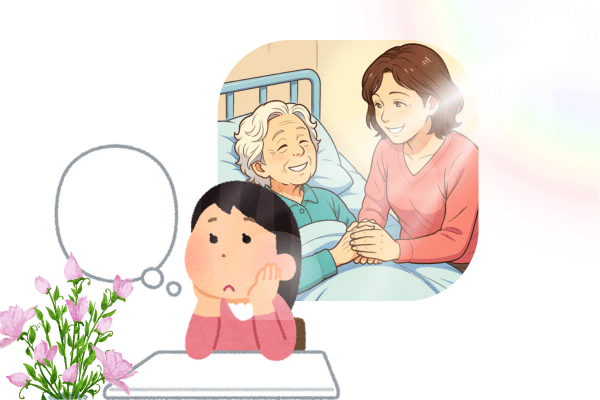
介護のノウハウは、母を見て
お母さんが、おばあちゃんの手をそっと握って言いました。
お母さん「おばあちゃん、私……もう無理」
長男の家で暮らしていたおばあちゃんが、私の家に来たのは、私が中学に入った頃でした。
来たばかりの頃のおばあちゃんは、台所に立って、いつものように洗い物をしていました。

おばあちゃん「おかえり、ランドセル置いたら手を洗っておやつ食べ(笑)」
けれど、80歳を超えた頃から、徐々にベッドにいることが時間が長くなっていきました。
トイレに行くのもしんどくなって、ベッドの横にポータブルトイレを置いて、母がトイレ介助をするように
10分おきのトイレ介助が1ヶ月続いた、ある日の午後。
母は、ついに「おばあちゃん、おむつ付けてくれる?」
おむつを使うようになってから、おばあちゃんの認知機能は、少しずつ弱っていきました。
けれど、母にとっては、時間にゆとりができたようでした。
週に三回ほど、短い息抜きの時間を取ることができるようになったのです。
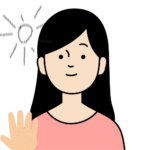
おばあちゃん、ちょこっとだけ息抜きにパチンコ行ってきていい?
おばあちゃん「ああ、いいよ」
母が外に出ていくと、奥の部屋から弟の良(りょう)が出てきました。
何も言わずに、おばあちゃんのベッドの横で、好きなプラモデルを組み立て始めます。
そのまましばらく時間が過ぎて。
ふと弟がベッドの方を覗き込むと
おばあちゃんのおむつが、外にはみ出して
ベッドは、びしょびしょに濡れています。
慌てる弟……
しばらくは、どうしていいかわからなかったけど、そばにあった受話器を取りました。
チュルルルル……………(コール音)
”かちゃ”
パチンコ屋の店内では、
「チャラララ〜♪」と、耳に残る J-POP が少し大きめに流れています。
玉の音と混ざって、電話の声は聞き取りにくい。
しばらくすると、店内アナウンスが響きました。
「〇〇さま、〇〇さま。ご家族の方からお電話です。カウンターまでお越しください。」
お母さん「えー、今良いところなのに…… (間)」
「……何かあったんやね」
高齢者が『おむつを外す』とき──母の介護で見えたもの
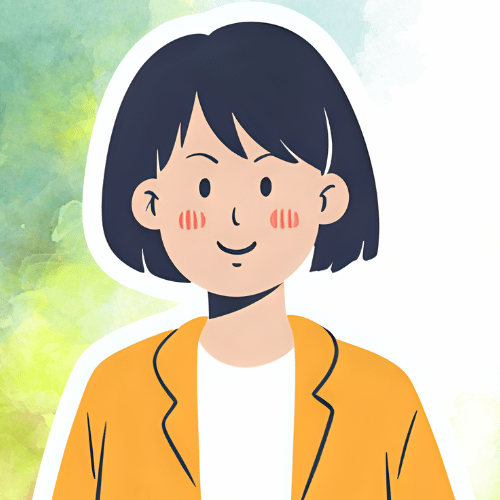
介護は、当時も今も、根っこの部分は変わらないんですね

そう。母は、祖母の排泄ケア(排泄介助)で、当時は、ストレスを感じていたと思います。
少し笑みを浮かべて、トメ子さんは続けます。

だから時々、息抜きに外へ出ていたんです
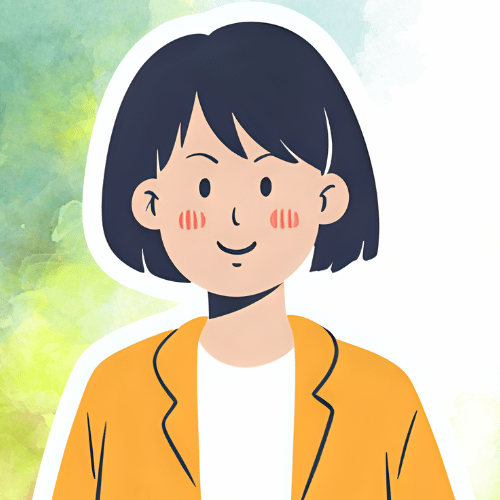
でも、その隙に……おばあさまがおむつを外してしまったと

はい。幸い、訪問看護師さんや妹たちの協力もあって、深刻にはならずに済みましたけどね
少し間をおいて、トメ子さんは言葉を選ぶように話し出します。

私なりに、高齢者がおむつを嫌がるの理由と対策を考えたので聞いてくれますか
おむつを外してしまう主な原因(トメ子が考える4つの理由)
ここからは、大正製薬の『エリエール』の記事から、代表的なものをピックアップしました。
高齢者が「おむつを外す」主な4つの理由
| No. | 原因のタイプ | 状況・心理 | 具体的な内容 |
| ① | 「情けない」と感じる自尊心の痛み | 感情は残っており、「おむつ=恥ずかしい」と感じる | 「情けない」「恥ずかしい」と思い、自尊心が傷つくことで、おむつを外してしまうことがある |
| ② | 「なぜ必要なの?」という困惑 | おむつの必要性を理解できない | 「下着を外す=排泄の準備」と誤認し、無意識に外してしまうケース |
| ③ | モコモコした違和感・不快感 | 身体的な装着ストレス | 吸収量が多くモコモコする、締め付けが強い、濡れた状態が続くなどで不快に感じる |
| ④ | 肌のかゆみ・皮膚トラブルのSOS | IAD(失禁関連皮膚炎)などの肌トラブル | アンモニアや消化酵素の刺激でかゆみが起き、外してしまうことがある |
認知症の方のおむつ外し対策(トメ子流・優しい3つのコツ)
大切なのは、介護を受ける方を感情的に責めたり、急かしたりしないことだと思います。
おむつを外す行動の裏には、「不快」「恥ずかしい」「わからない」といったサインが隠れています。
少しの工夫で、本人の負担も介護する側のストレスも軽くできます。
- 言葉を工夫して、心理的な抵抗を軽くしてあげましょう
- 排泄のタイミングを記録し、「急な対応」を減らしましょう
- 肌と体に合ったおむつと、優しいスキンケアで不快感をなくしましょう
① 言葉を工夫して、心理的な抵抗を軽くしてあげましょう
「おむつ替えようか?」ではなく、「気持ち悪くない? 少しきれいにしようか」と気持ちに寄り添った声かけを。
替えるという行為より、気持ちよくなることを意識させる言葉が効果的です。
② 排泄のタイミングを記録して、「急な対応」を減らしましょう
1日の排泄パターンをメモしておくと、「この時間帯はトイレに誘導」「このあと交換」と予測して動けるようになります。
介護する側が落ち着いて対応できると、本人も安心して任せられます。
③ 肌と体に合ったおむつと、優しいスキンケアで不快感をなくしましょう
素材の違いで、蒸れや締め付けが軽減されることもあります。
また、排泄後はおしり拭きや保湿剤でのスキンケアを習慣に。
IAD(失禁関連皮膚炎)の予防にもつながります。
トメ子メモ
介護の現場で感じたのは、「完璧にやろう」とすると心が持たないということ。
優しくとは、相手にも自分にも無理をさせないという意味なんだと思います。
母の介護は、今につながって
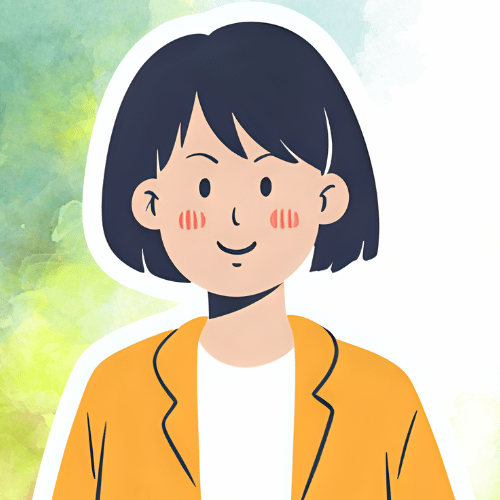
おばあさまの介護の経験が、今のトメ子さんの介護にも生きているんですね

そうですね。あの頃の母の様子を見ていたから、介護するって寄り添うことなのかなって
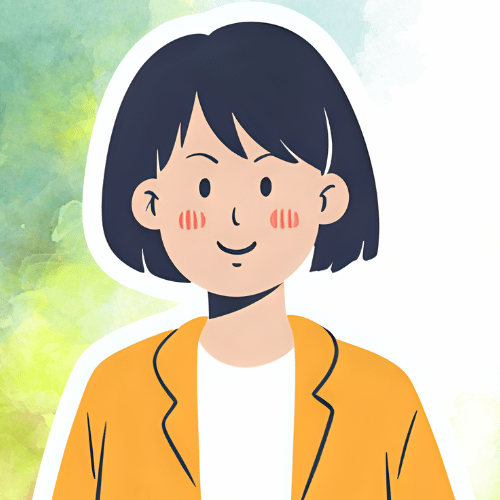
でも、実際の介護って、思うようにいかないこともありますよね

はい。いくら気をつけていても、弄られたり外されたりが続くと、本当に大変だったと思います。
少し間を置いて、トメ子さんは穏やかに続けます。
トメ子「あの頃は、周りの勧めもあって福祉用具のミトンやつなぎなんかも使ってたと思うんですが、家族としては、苦しい選択だったんじゃないでしょうか」
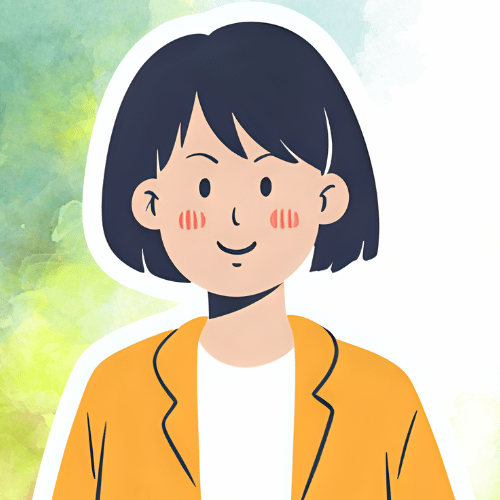
だったら、今なら良い福祉用具ありますよ
見た目は普通の下着、おむつ外し防止に『白寿』という選択
ある日、トメ子さんは友人とお茶を飲みながら、こんな話を聞きました。
その方は、介護施設で20年以上働くベテランの看護師さん。
長年、いろんな利用者さんと向き合ってきたそうです。

久しぶり。最近、仕事どう?
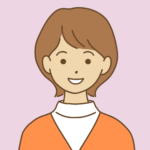
相変わらずよ。この前なんてね、おむつを破っちゃって、そこらじゅうポリマーだらけ!
「掃除と片づけで1時間以上かかっちゃったの。」

うわぁ……大変だったね
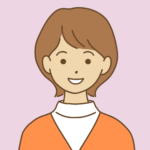
でもね、その方、普段はすごくダンディーでおしゃれなの。だからつなぎパジャマとか、本当に嫌がるのよ

見た目、気になるもんね……
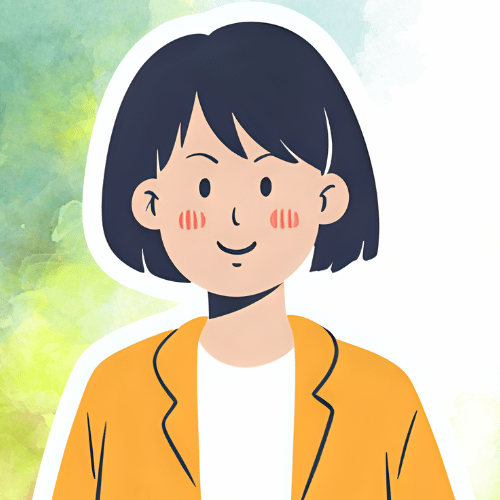
そういう話を聞くと、本当に切なくなりますよね……。
「でも最近は、おむつ外しを防ぐのに役立つ下着もあるんですよ。」
これからの介護に「介護インナー白寿」という選択肢を
今回、『認知症おむつ外し』の記事を書いてて、他にできることは検索していると
『着る人にもやさしく、介護にもやさしい介護用下着』を見つけました。
介護用品ウサギ屋の公式ホームページは、こちらhttps://usagiya99.com/detail_99.html
構造のポイント
- 背面にあるマジックテープが、着用者の体重で自然に圧着される仕組み
- おむつを外す・便を触ってしまう等の行動を、無理なく防いでくれる
『白寿のインナー』公式サイトの口コミをみて
評価は全体的に高め(星5が多い印象)
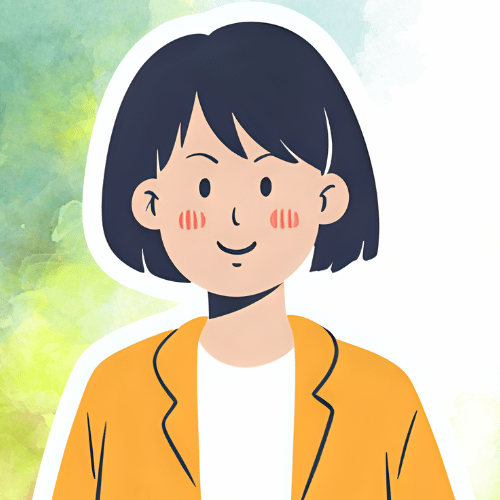
全体に、「洗い替えに2枚目も購入したい」といった声が多く、リピート率が高い印象でした。
*ただ、良い面だけでなく、いくつか気になった点もありました。
つまり、「完璧」ではないけれど、丁寧に扱えば有効な選択肢になりうるというのが、リアルな声です。
昔と今、変わらない『介護の思い』
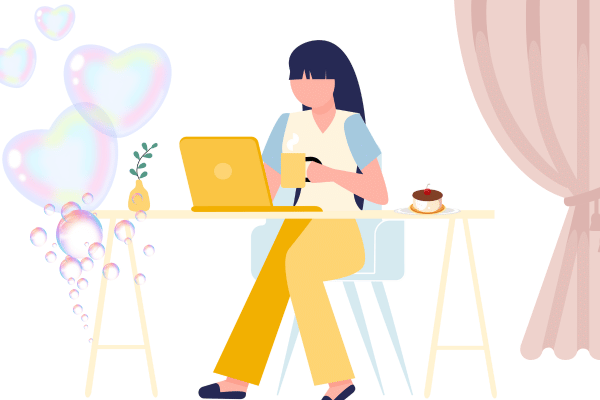
今回のお話はここまで
おむつを外す高齢者の気持ちも、介護する側の気持ちも、どちらも真っ直ぐなんですよね。
どんな思いで、手を伸ばしたんだろう。
どんな気持ちで、その手を受け止めたんだろう。
そんなことを考える時間も、介護の一部かもしれません。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。