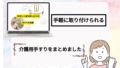認知症の義母(ばあちゃん)は、『介護用おむつ』を使うことに抵抗を感じていました。
千葉の姉の家にいる時から、姉が勧めて「そんなもの、使わん!」そう言って、姉の買ってきた『介護用おむつ』をゴミ箱に捨てていたそうです。
その、『介護用おむつ』を嫌がる行為は、続いてて
認知症の症状が、義母の「パンツを汚した」記憶を奪ってしまうので、さらに使ってもらう事を難しくさせていきました。
もし、義母が元気なうちに姉たちと『介護用おむつ』や『介護のこと』話してくれていれば、もっと違った形の暮らしを続けれたのか。
そう思ってしまうのです。
今回は、私の介護の体験談を通して、親の元気なうちに『介護のこと』『介護用おむつのこと』を話すことの大切さを知ってもらい
今の『介護用おむつ』の種類を知ってもらえば、それほど抵抗感じなくなるなるんじゃないでしょうか?
最後に男性の認知症患者さんへのアプローチーの仕方を現役看護婦さんから聞いたアドバイスを紹介していますので、そちらだけでもご覧ください。
では、義母との介護体験より、どーぞ
高齢者が、介護用おむつを拒否するのは何故?
デイサービスで履いてきたオムツだけど、忘れるばあちゃんは困惑気味。

私は、こんなの履いた覚えがない!誰や、こんなの
私が選んだ対応
「今朝、ばあちゃん便が出ないって言ってたから、デイサービスで浣腸してもらって、汚したらあかん。っと思って、職員さんが履かしてくれたんと違うか。わからんけど」
それでも、興奮がおさまらない。
仕方がないので、私はついに「介護用おむつの存在」を無かったことに

ああ、このオムツが嫌だったんだね。じゃあ、パンツに履き替えようか?
そのときは、うまく話題を変えてやり過ごしました。
ですが、下着を汚すたびに、私もばあちゃんも精神的にも肉体的にもしんどくなってくるので、なんとか受け入れてもらいたくて、

ばあちゃん、88歳なんやから、紙パンツ使うの、なんにもおかしいことちゃうよ。
とか、
「むしろ使ってくれたら、私たち、ほんまに助かるんよ」
と、言っても

こんな、ゴワゴワしたの使うんやだ。まだ、そんなにもうろくしてない!
強く拒否されて、汚れたパンツを洗面所で、皆んなに気付かれないように洗いながらため息が出た。
おむつを嫌がる理由;3選
① 「自分はもうダメなんだ」と烙印を押された気持ち
ばあちゃんは、「自分はまだしっかりしてる」と思っていたのに、
オムツの提案はそれを全否定されるように感じになった。
* 介護用オムツ=自分の終わりの始まり、敗北宣言のようなもの。
② 世間から「もう無理」と判断されたような屈辱感
自分の意志ではなく、「他人(家族や世間)」に“介護される側”と決めつけられたような感覚。
* 介護用オムツ=自分の尊厳を他人に決められる悔しさ。
③ 恥ずかしさと「自分らしくない」違和感
下の世話は人として“最も見せたくない部分”であり、
ばあちゃんにとっては「そんな姿、見せるのも見られるのも絶対に嫌」
* 介護用オムツ=“恥の象徴”であり、自分らしさが失われる象徴。
介護が始まる”前に”できる事は

まずは会話する事から、「もしものとき」の話をしてみる
親が元気な時だからこそ、「もしもの時」を自分ごととして、家族で話してみて下さい。
今だったら、お互いの思いや希望を素直に伝え合うことができます。
大切なのは、完璧な答えを出すことではなく、まずは会話を始めてみることが大事だと考えられます。
【厚生労働省 2022年発表の推計より】
厚生労働省の発表によると、認知症になる確率は80歳を過ぎると徐々に上がり、85歳を超えるとおよそ**3人に1人(32.8%)**が認知症になると推計されています。
さらに、軽度認知障害(MCI)を含めると、将来的に認知機能に何らかの影響が出る高齢者はもっと増えるとも言われています。だからこそ、「まだ早い」と思わずに、元気な今こそ話しておきたいのです。
紙パンツや尿漏れパッドを一緒に試してみる
今、若い人でもちょっと遠出に出かける時などは、紙パンツや尿俺パットを普通に活用しています。
まず、自分で試してみて
「今は、こんなに使いやすくなってるんだ」と言う事を、親子で実感してみて下さい。
かなり進化していますよ。(実は、私も利用しています)
「安心のために」という伝え方の工夫
どんな時でも、あったら安心紙パンツ♪
お出かけの時なんかは、強い味方になると思いますよーー。
そんな感じに、軽く日常の生活に取り入れてみて下さい。
失敗談ではなく「予防」として紹介する
「失敗してからじゃ、本人も気まずくなっちゃう。だから、まだ大丈夫なうちに少しずつ慣れてもらえると安心です。“みんな使ってるよ”っていう一言も、案外効きます。」
買い物のついでに見せておくだけでも違う
一緒にドラックストアーに入って、

これ、草薙くん(草彅剛さん)がCMで宣伝してたやつ!
「テレビで見て気になってたんですよね〜、今は色んな種類あるんだね」
みたいに、軽く、軽く、
紙おむつなんて、大したことないないんだよ。って事を伝え続けるのが大事だと思います。
使う場面によって変わる3パターンの介護おむつ
ドラックストアーやネットショッピングを見て回っても種類も多くて、何をどう選んでいいかわからないと思うんです。
もしよかったら、こちらの記事を参考に選んでみてはいかがでしょうか?
介護用品を比較検証した記事mybestのブログです
介護用品としてだけじゃなく、若い人でも使う時代に

最近は若い人でも、旅行や長時間の移動などで紙パンツを使う方が増えています
実際、私自身も長距離移動のときに使ったことがあって、「これがあると安心できる」って思ったんですよね。
つまり、[紙パンツ=年寄り・介護用]っていうイメージ、もう古いのかも。
今では、“便利な下着”として、年齢問わず使われる時代になってきているんです。
3パターン:用途に応じて使い分けられる介護用品
では、紙パンツや紙おむつにはどんな種類があるのか?
薬局で聞いた話をもとに、わかりやすく3つに分けてご紹介します。
パッドタイプ
・下着や紙パンツの中に敷いて使うタイプ
・軽い尿モレや“念のため”用にちょうどいい
・おむつ感が少なく、見た目も普通の下着に近いので、受け入れやすい
紙パンツタイプ(リハビリパンツ)
・立って歩ける人向けの、履くタイプのおむつ
・見た目も履き心地もかなり“普通のパンツ”に近い
・最近は超薄型で、ズボンの下からでも目立ちにくいものが主流
テープ式タイプ
・寝たきりや自力での着脱が難しい人向け
・横になったまま交換できるため、介護する側にとっても負担が少ない
・吸収力が高く、夜用や長時間用などもあります
もちろんそれぞれにメリット・デメリットはありますが、少しずつ慣れていけるのが嬉しいところです。
最後に、快適な介護生活への一歩として
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
最後にひとつ。ここまでの話は、認知症になる前の母のような女性には、比較的伝わりやすい内容だと思います。
ただ、男性に対するアプローチの方が難しいと実際の看護師さんが言っていました。
プライドの高さや、自尊心の強さが影響しているのかもしれません。
私が思う男性へのアプローチは、“下から、やわらかく”がコツです。
たとえば──
「あなたは優しいから、きっと私が困らないように使ってくれるよね」
「ごめんね。嫌な思いをさせてしまって、私もつらいのよ」
……そんなふうに、娘や配偶者から言われたら、男性として使わないわけにはいかないかもしれません(笑)
ここまで読んで頂きありがとうございました。
義母と暮らした1年間の記録を「気楽な認知症介護」にまとめましたので、お時間のある時にお楽しみください。