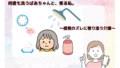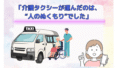「在宅介護の限界って、何だと思いますか?」
食事の介助?
お風呂に入れること?
夜中の徘徊や、急な体調変化?
どれも大変です。実際、私も経験してきました。
でも――
排泄のトラブルは、在宅介護をしていると、ほぼ必ずぶつかる大きな壁です。
本人は、プライドがあるからこそ受け入れにくく、介護者側にすると、生活のリズムも心の余裕も、一気に持っていかれるような衝撃があります。
それでも家族は、
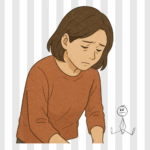
自分さえ、黙って我慢すれば…
と、汚れた下着を洗い、何もなかったように笑顔で接しようとします。
でもね、排泄の問題は、家族だけではどうすることもできない段階に来ている。
それを、“限界”だと認めてもいいんじゃないかな。って、思うんです。
今回は、認知症家族の数だけある、排泄トラブルの乗り越え方を紹介しつつ、
私自身が、義母と「もう暮らせなくなった」と感じた瞬間についてもお話しします。
認知症家族の数だけ、排泄との向き合い方がある
排泄のトラブルにどう向き合うか――
・母との会話を避けてきた結果、いきなり始まった「母親の失禁」こうなる前に、母親と会話をしていれば……
・一人っ子だったから、最後まで親の介護から逃げなかった林檎ちゃんの壮絶なる母親の認知症による排泄トラブル
・まだまだ、元気なばあちゃんですが、その性格と認知症の症状に「排泄トラブル」が加わって、ムリってなったトメ子の話し
順に紹介していきます。
母親がうざい、会話を避けてた丸尾の話し(仮名)
昔から口うるさくて、話すたびに説教じみたことを言われる。
だから、気づけば自然と、母と会話するのを避けるようになっていたそうです。
ある日、母が失禁したままリビングで座っていた。
「え?何で?」と思って声をかけたら、
母は、何が起きてるのかわからない様子でどこか他人事のような、ぼんやりとした目をしていた。
その時、初めて母が介護状態になってる事に気づきました。
そして、心のどこかで思ったんです。
「もっと母と会話していれば、こうなる前に、何か異変に気づけたのかもしれない」と。
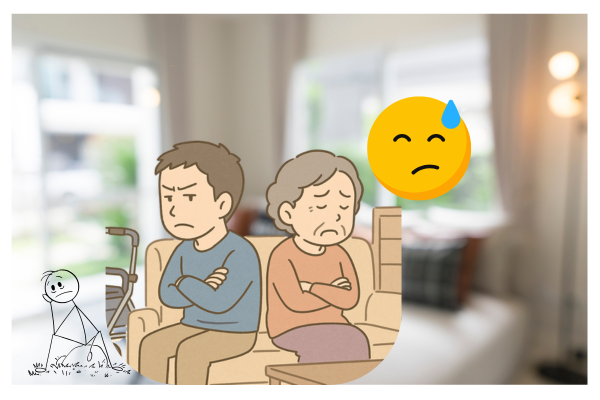
一人っこで、お父さんとお母さんのW介護をしていた林檎ちゃん(仮名)
昔はちょっとヤンチャだったという林檎ちゃんは、一人っ子です。
友人が多く、何かあってもすぐ誰かが駆けつけてくれるような人柄で、
周りに助けてもらいながら、【認知症のお母さんと、高齢のお父さんの“ダブル介護”】を続けていました。
お母さんは、林檎ちゃんにそっくりのしっかり者で、綺麗好きな女性。
70歳を過ぎても、その美しさは変わらず、

ちゃんとした格好で外に出たい
が口癖だったそうです。
そんなおばちゃんが、ある時病気を患い、その影響もあって、少しずつ認知症が進行していきました。
最初は、自分の状況も理解できていて、

迷惑かけて、ごめんね
と、まだ言葉も交わせていたけど、徐々に娘の顔もわからなくなっていきました。
林檎ちゃんが当時、特に大変だったのが「排泄の問題」だったと言います。
「綺麗好きだった母は、“汚したこと”を人に知られたくなかったんだと思うけど」

その時は、家の中が酷い状態になって…..。
「兄弟がいれば、って思うけど….。」
そんな林檎ちゃんが最後に選んだのは、病院への入院という決断でした。
*「精神病院」と聞くと、重苦しいイメージを持たれがちですが、多くの病院はそんなことはありません。
患者さんと介護者、どちらも守るための場でもあるんです。

病院に入れたとしても、罪悪感を持たんといてね
長谷川医師の著書から、ばあちゃんの事を思う
このエピソードは、長谷川和夫先生のご家族が綴った「なかまある」の記事から、特に印象に残った一文を紹介します(参考:「父は認知症になることができた」息子が語る医師・長谷川和夫の姿(上))
「父が言った『認知症が始まったことで、自分の中の“確かさ”が揺らぐ』という言葉には驚きました」
この一文を読んで、私はふと思いました。
ばあちゃんは、どこで「自分の中の“確かさ”」に不安を感じたんだろう。
私たちが一緒に暮らし始めた時、ばあちゃんはすでに、アルツハイマー型認知症で、症状はかなり進んでいました。
さっき言ったことを忘れ、何度も同じことを聞いてきます。
それでもばあちゃんは、こう言い続けていました。
「私はボケてない」
「どこも悪くないのに、お前らがばあちゃんをボケにするんや」
…そう言っていた頃には、娘とはもう一緒に暮らせなくなっていたんです。
そして今日。
何度も排泄を失敗するばあちゃんに、私はとうとう声を荒げてしまいました。

もう、ええ加減、紙おむつを受け入れて!
すると、ばあちゃんは汚れたパンツを手に持って、こう言いました。

お前が汚して、ばあちゃんのところに置いたんやろ
その瞬間――
私の中で、何かがポキッと折れたんです。
それが、「もう、ばあちゃんとは暮らされへん」って思った瞬間でした。
📚 おすすめの本
「確かさが揺らぐ」という感覚――
親のちょっとした変化に気づいたとき、あるいは将来の自分に重ねてしまったとき、心にすっと入ってくる言葉です。
認知症の第一人者・長谷川和夫先生がご自身の体験をもとに綴った一冊。
専門家として、そして当事者として、「認知症と共に生きるとは何か?」を静かに教えてくれます。
親が施設に入ったとしても介護の形が変わるだけ
ばあちゃんが施設に入って、2か月が経ちました。
初めのころは「帰る」と言って、すごい力で鍵のかかった扉をこじ開けようとすることもありました。
それが、少しずつ落ち着きを取り戻し、今では日中、ほかの利用者さんとおしゃべりをしたり、レクリエーションを楽しんだりしています。

毎日が“1日目”のように見える瞬間もありますが、そんなことはありません。
スタッフさんによると、今では夜7時になると自分の部屋に戻り、そのまま朝まで眠っているそうです。
要介護度は2から3に変わり、現在は特別養護老人ホームの入所待ちです。
施設によって対応は異なるかもしれませんが、ばあちゃんが通っている小規模多機能型施設では、このままの形で長期の預かりも可能とのことです。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
三段腹トメ子